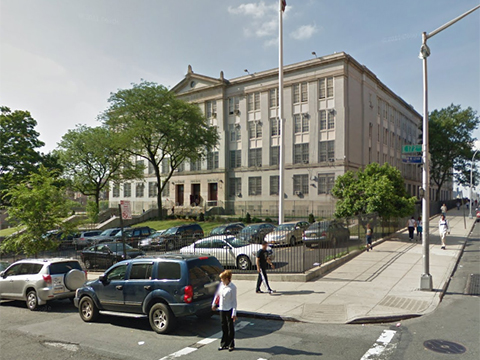【考察・検証】ボツになった『博士の異常な愛情』のタイトル案

キューブリックのノートに残されていた『博士の異常な愛情』のタイトル案 (1)Doctor Doomsday (2)Don't Knock the Bomb (3)Dr. Doomsday and his Nuclear Wiseman (4)Dr. Doomsday Meets Ingrid Strangelove (5)Dr. Doomsday or: How to Start World War III Without Even Trying (6)Dr. Strangelove's Bomb (7)Dr. Strangelove's Secret Uses of Uranus (8)My Bomb, Your Bomb (9)Save The Bomb (10)Strangelove: Nuclear Wiseman (11)The Bomb and Dr. Strangelove or: How to be Afraid 24hrs a Day (12)The Bomb of Bombs (13)The Doomsday Machine (14)The Passion of Dr. Strangelove (15)Wonderful Bomb (1)皆殺し博士 (2)爆弾をノックしないで (3)皆殺し博士と彼の核賢者 (4)皆殺し博士がイングリッド・ストレンジラブと出会う (5)皆殺し博士:または必要もないのに第三次世界大戦を始める方法 (6)ストレンジラブ博士の爆弾 (7)ストレンジラブ博士の天王星の秘密の使い方 (8)私の爆弾、あなたの爆弾 (9)爆弾の救済 (10)異常な愛情:核賢者 (11)爆弾とストレンジラブ博士:またはどのように一日の24時間を恐れたか (12)爆弾の爆弾 (13)皆殺し兵器 (14)ストレンジラブ博士の情熱 (15)素晴らしい爆弾 うーん、直訳だとちょっと意図が分かりにくいものばかりですね。(2)はロック映画として有名な『Don't Knock the Rock』に引っ掛けているのかも。配給が同じコロンビアですし。(3)も『Wisman』だとワイズマンという人名、『Wise Man』だと賢者という意味ですので、ダブルミーニングかも知れません。「核賢者」なんていかにもキュ...